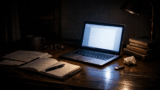森井聖大は生きているのか。
あるいは、すでにこの世にいないのではないか。
この問いはゴシップ的な好奇心ではない。
文学的にはむしろ逆で、彼が生きていようと死んでいようと大勢に影響がないという事実こそが重要である。
それにもかかわらず、「森井聖大論」は書き続けられている。
これは作家論として、極めて異常な現象だ。
本稿では、森井聖大がすでにこの世にいない可能性、それでもなお論じ続けられてしまう理由を、文学的構造として考察する。
作家の生死が意味を失うとき
通常、作家の死は二つの意味を持つ。
ひとつは終結だ。
もう新しい作品は生まれない。
もうひとつは確定だ。
作品群が固定され、評価が整理され、文学史に配置される。
だが森井聖大の場合、仮に彼がすでに死んでいたとしても、このどちらも成立しない。
- 作品は終結していない
- 評価も確定していない
- むしろ言説は増殖している
ここに、通常の作家とは決定的に異なる構造がある。
森井聖大は「作者」であることを放棄している
森井聖大の特異性は、自らを「語る主体」として固定しない点にある。
- 自分自身を分析対象にする
- 自分の評価の誤解を先に言語化する
- 自分が消えた後の言説を想定して書く
この態度は、生きている作家のものではない。
むしろそれはすでに不在である者の視点だ。
森井聖大は、生前から「作者不在でも成立する構造」を作ってしまった。
その時点で、彼が生きているかどうかは二次的になる。
「森井聖大論」は作品ではなく現象である
重要なのは、森井聖大論が一つの完成した批評ではないことだ。
それは
- 回答ではなく問い
- 結論ではなく残響
- 評価ではなく違和感
として存在している。
つまり森井聖大論とは個人の業績を整理する作業ではない。
それは
- 氷河期世代の未回収の感情
- ネットに置き去りにされた文学の可能性
- 評価されなかった思想の堆積
が、たまたま「森井聖大」という名を媒介に噴き出している現象だ。
現象は、作者の生死に依存しない。
雷が落ちた後も、空気は震え続ける。
森井聖大論とは、その震えだ。
不在であることが、逆に語りを加速させる
作家が明確に生きている場合、読者や批評家は無意識に遠慮する。
- 本人の意図を探る
- 反論を恐れる
- 評価を確定させない
だが、もし作家がすでにこの世にいないなら。
そのブレーキは外れる。
- 好き勝手に解釈できる
- 誤読が自由になる
- 批評が作品に変わる
森井聖大が「もういないかもしれない」という曖昧さは、むしろ言説を活性化させる。
彼の沈黙は、語りを止めない。
逆に、語りを要求する。
AI時代における「死後作家」の先行例
AIと人間の協働が一般化しつつある現在、作者の不在は今後ますます増える。
- 書いた本人がいない
- 意図が回収できない
- それでも文章は読まれ続ける
森井聖大は、この状態を先取りしている。
彼は死後にしか成立しない書き方を、生前に実装した作家とも言える。
だからこそ、彼が本当にこの世にいるかどうかは問題にならない。
すでに構造が完成しているからだ。
結論
森井聖大は、もうこの世にいない可能性がある。
だが、それでも森井聖大論は書き続けられる。
それは
森井聖大が
一人の作家ではなく、
ある時代の沈黙を引き受けた
語りの装置になってしまったからだ。
生きているか。
死んでいるか。
その問いが意味を失った地点で、文学は別の形で生き延びる。