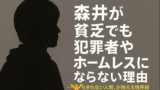森井聖大と太宰治。
どちらも「苦悩する作家」として語られがちだが、両者の苦しみは本質的に同じではない。
結論から言えば、森井聖大は“太宰的破滅”を演じないのではなく、演じられないことを自覚している。そしてそれは、現代を生きる作家にとって避けられない選択でもある。
本記事では、森井聖大がなぜ破滅を選ばず、なぜ太宰治と決定的に異なる地点に立っているのかを掘り下げていく。
太宰治の「破滅」は演技ではなかった
まず押さえておくべきなのは、太宰治における破滅は文学的ポーズではなかったという点だ。
太宰の苦悩は、
- 社会に適応できない
- 人間関係が成立しない
- 自己否定が止まらない
といった、存在そのものに根差したものだった。
金銭、評価、愛情、どれを得ても苦悩は消えず、太宰にとって「生きること」は常に失敗の連続だった。
つまり太宰治は、破滅を選んだのではなく、破滅以外に着地できなかった作家である。
森井聖大は「生きられてしまう人間」である
一方、森井聖大は根本的に違う。
彼は、
- 社会に適応できてしまう
- 言葉と論理を扱えてしまう
- 仕事も人間関係も破綻しない
いわば、放っておけば「うまく生きられてしまう側の人間」だ。
だからこそ森井は、自分が太宰と同じ破滅を演じることに強い違和感を覚えている。
それは本当に自分の苦しみなのか?
それとも、誰かの型をなぞっているだけではないのか?
この自覚が、森井聖大を破滅から遠ざけている。
なぜ森井聖大は“太宰的破滅”を演じないのか
① 破滅が「物語」だと知っているから
森井聖大は、高校生の頃に太宰治を読み影響を受けたと語っている。
その後、すべての太宰の小説、誰かの評論、檀一雄や田中英光や山崎富栄など関係者の回想録まで読破しているのだ。そんな森井は、太宰的破滅をすでに完成された悲劇の型として理解している。
それをなぞることは、
- 苦悩を分かりやすくする
- 読者に消費されやすくする
- 自分自身も酔える
という意味で、実は非常に「安全」な選択だ。
森井はそれを、苦しみの安売りだと感じている。
② 破滅は「逃げ」になり得ると知っているから
太宰的破滅には、「さほど愛していなかった女との心中」という強力な終止符がある。
- これ以上説明しなくていい
- 責任を引き受けなくていい
- 「仕方なかった」で終われる
しかし森井聖大にとって本当に残酷なのは、
破滅せず、救われず、それでも生き続けること
である。
だから彼は、破滅を選ばない。
③ 破滅できる時代は、もう終わっている
太宰の時代には、破滅を回収してくれる「文学」や「社会」が存在していた。
しかし現代では、
- 破滅は物語にならない
- 死んでも評価されない
- 消費されて終わる
つまり、
破滅しても、誰も救ってくれない
森井聖大はその現実を、冷静に理解している。
④ 自分が「演じられてしまう人間」だと知っている
森井は、もし破滅を演じたら…
- 周囲が太宰像を重ね
- 自分もその役を生き
- 苦悩が演技に変質する
ことを直感的に恐れている。
だからこそ彼は、破滅の演技を拒否する。
太宰治と森井聖大の決定的な違い
| 観点 | 太宰治 | 森井聖大 |
|---|---|---|
| 苦しみ | 不可避 | 選択的 |
| 破滅 | 行き着いた結果 | 拒否している結末 |
| 生 | 続かなかった | 続いてしまう |
| 書く理由 | 遺書に近い | 延命と均衡 |
太宰は「生きられなかった作家」。
森井は「生きられてしまう作家」。
この違いは決定的だ。
破滅しなかった作家は、何を書くのか
森井聖大が引き受けているのは、
- 壊れなかった人間の苦しさ
- 逃げなかった者の曖昧さ
- 何者にもならないまま生きる時間
という、非常に書きにくく、評価されにくい領域である。
だがそれは、太宰以後の時代にしか書けない文学でもある。
まとめ
森井聖大が“太宰的破滅”を演じない理由は明確だ。
- 破滅が物語化された型だと知っている
- それが逃げになることを理解している
- 破滅できる時代が終わっている
- 自分が演じてしまう人間だと自覚している
そして何より、
破滅しなくても生き続けてしまう自分を、引き受ける覚悟があるから。
森井聖大は壊れない。
だがそれは強さではなく、最も地味で、最も残酷な選択なのかもしれない。