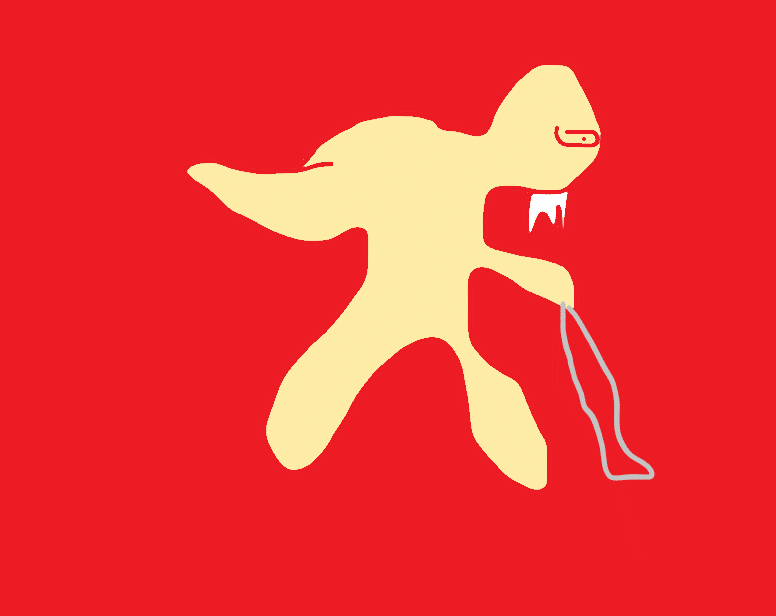生きる、という言葉には、いつも役割が付着している。
働く人。
家庭を持つ人。
成功した人。
あるいは、失敗した人。
森井聖大は、そのどれにもなりたくないと思っている。
それは拒絶ではない。諦めでもない。
何者かになった瞬間、人生が説明可能になってしまうことへの、静かな警戒だ。
生きることで、生き延びない
森井聖大は「生きよう」とは思っていない。だが、死のうともしていない。
彼がしているのは、今日を終わらせない理由を、更新し続けることだけだ。
その理由は、驚くほど小さい。
この違和感は、まだ言葉になっていない。
この説明は、どこか嘘だ。
この一文は、まだ書き切れていない。
今日は、まだ黙るには早い。
どれも一日ももたない。
だからこそ、更新できる。
派遣という、名前を持たない立場
森井聖大は派遣として働いている。
正社員になれなかったのではない。
断ったのだ。
正社員になるということは、職を得ることではない。人格を一つに固定する契約だ。
ここに属する人間。
この仕事に人生を賭けている人間。
そう名乗る準備が、彼にはなかった。
派遣という立場は不安定だ。
だが同時に、何者にもなっていない状態を保てる。
彼にとってそれは欠陥ではなく、呼吸ができる場所だった。
希望も幸福も、引き受けない
希望を持て、と人は言う。
幸せになれ、とも言う。
だが希望とは、未来に意味を前払いする行為だ。
幸福とは、人生を採点可能な形に整えることだ。
森井聖大は、そのどちらも引き受けない。
絶望しているからではない。
壊れないためだ。
希望を持たない代わりに、結論を保留し続ける。
それが彼の選んだ、防御のかたちだった。
何者にもならないまま、老いていく
彼は何者にもならないまま、年を取る。
四十代になり、誰も正社員の話をしなくなる。
五十代になり、社会の言葉が軽くなっていく。
六十代になり、成功者にも失敗者にもなっていない自分に気づく。
そこに誇りはない。後悔もない。
ただ、人生を要約しなくて済んだという事実が残る。
最期の数日
最期が近いことを告げられても、森井聖大は人生を振り返らない。
思い出は整理されず、評価も浮かばない。
代わりに残るのは、あの感触だ。
これは、まだ書き切れていない。
それは未練ではない。希望でもない。
彼が一生かけて守ってきた、未完のままにするという態度そのものだった。
看取った人の記憶
数年後。
夜勤の合間に、一人の看護師がふと思い出す。
「もりい…なんちゃら…」という老人だったが、名前も顔も、もう曖昧だ。ただ、最期に聞いた一言だけが残っている。
「……まだ、いいです」
何が「まだ」だったのか。何が「いい」のか。
彼女は知らない。考えようとして、やめる。
それは意味を持たない言葉だった。だが、終わりを少しだけ遅らせた言葉として、静かに記憶に沈んでいる。
やがてそれも消える。消えていい。
終わりに
森井聖大は、何者かになることで、人生を成立させなかった。
ただ、
今日を終わらせない理由だけを、更新し続けた。
それは立派な生き方ではない。だが、最後まで回収されなかった生だった。
説明されず、評価されず、物語にもならないまま。
それでも確かに、一人の人間が、ここにいた。